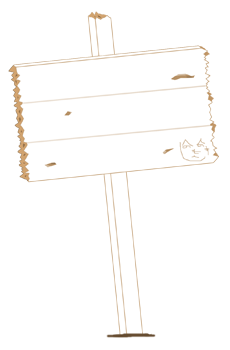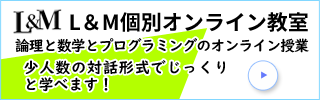学問と論理9(ギリシャの合理主義2) -なぜ・なにを・どう学ぶのか-
前のページ:学問と論理8(ギリシャの合理主義1) -なぜ・なにを・どう学ぶのか-
目次へ
この一連の議論、問答においてソクラテスは、むやみやたらに質問を繰り返していたわけではなく、対話者の理解の不完全に見える部分に対して問い掛けをし、より深い理解があるのか否かを確認しょうとする、一貫した姿勢を保っていました。つまり、ソクラテスとしては、自らの納得できる回答があるかないかの一点を問題にして、真理を探求していたのですが、ついにその回答はなく、逆に、それを見出しているかのように振る舞っていた権威ある人々の問題を明らかにしてしまいました。そのため、ソクラテスは、結局、その権威を傷つけられた人々の反感を買い、扇動の罪で刑死させられてしまうのですが、しかし、ソクラテスの見い出したこの、無知の知という考え方と、とくにそれを確かめるために用いた問答法という物事の理解を深めていく議論の仕方、あるいはその思考方法は、弟子たちの教育に生かされ、その能力を大幅に高めていくことに繋がりました。そして、このソクラテスの考えと行動が合理主義、ギリシャの学問のさらなる発展の扉を開くことになりました。
ここで少し、ソクラテスの問答法について、それが如何に理にかなったものであるか、誤解のないように解説を加えたいと思います。ある意見を議論を通して正しいと認めるのに、何の理由もなければその正しさは理由のない合意であり、その正しさの理解や、少なくとも正しさの証明はできていないと言えます。そこで、その意見に関係する事実や考え方の中から、その意見の正しさを証明できる理由を探し出すことになるのですが、その理由は、少なくともその意見よりも、より確からしい正しさを持たなければ理由になりません。なぜなら、より正しくないもので、より正しいものを証明することは、滑稽なほど間違っているからです。さらに、たとえ、良い理由が見つかったとしても、その理由の正しさについては、元々の意見に対して行ったのと同じように議論、問い掛けを行うことができます。つまり、繰り返し理由の理由を問うということです。そして、それは際限なく問い続けることができるわけで、偏屈なようですが、厳密に考えると、このような論理に人の思考は縛られていることを認めざるを得ないと思います。つまり、理屈を持って何かを理解しょうとすれば、どこかで理由なしに認める最も確からしい事実や考えが必要になってしまいます。けれど、その事実や考えが絶対的、完全に正しいということは、決して証明できない。つまり、完全な理解ではない。これが一歩踏み込んで考えた場合の、ソクラテスの説く、人の知恵の限界、無知の知の意味であると思います。しかし、同時にこの思考の取り組み、問答法は、より確からしい理由を探させる、人の考えを洗練させる良い方法になること、それは間違いないだろうと思います。
ソクラテスの弟子にはプラトン、さらに孫弟子のアリストテレスという大学者が生まれました。とくに論理学においては、アリストテレスが、論理的な推論、演繹規則を初めて定型化するという大成果を生み出しています。有名なアリストテレスの三段論法とは、例えば、人は賢い、あなたは人である、したがって、あなたは賢いという論法のことを指しますが、この三段論法だけではなく、どのような推論が一般的に正しいかということを、これまでのギリシャにおける議論を詳細に考察して、一定の形式にまとめ上げました。アリストテレスの行った推論、演繹規則の定型化は、一つの論理体系のひな型を生み出したことになり、それ以後、例えば、AならばBである、BならばCである、Cならば、、、YならばZである、したがって、AならばZである、などといった前提から結論に至るまで、複雑に構成される命題による推論、つまり、論理的に物事を捉え、考え、表現することを、多くの学者ができるようになりました。これは、私としては、特にソクラテスの問答法による、より明らかな根拠を見い出そうとする訓練が、一般的に三段論法といわれる論理の萌芽を生み出す、論理の型枠を研究させる動機付けとなったのではないかと思っています。そして、この論理体系の洗練は、あっという間に一つの頂き、数学の名著であるユークリッドの原論を生み出すことに繋がっていきました。
ユークリッドの原論とは、エジプトのアレキサンドリアの数学者ユークリッドが、それまで知られていたギリシャ数学を集大成した本と考えられています。幾何や数論などを含み、当時の最先端の数学的内容が掲載されています。ただ、ユークリッドの原論の価値は、その数学的な内容のみならず、その論理的構成において、その後の学問の枠組みに決定的な影響をもたらしたことです。その論理的構成というのは、それまでの学問や議論は、テーマに関わる様々な主張について根拠は述べるものの、根拠の正しさ、確かさの吟味をあまりしていなかったり、主張や根拠の互いの関係性を整理せずに構成が入り乱れたりしていました。それに対して、ユークリッドの原論は、幾何や数論などの分野で、当時においては、できる限りの前提をあぶり出し、皆が確かだと認めざるを得ないような主張を公理や公準として定め、その上で、公理や公準のみを根本的な根拠として、さらに、すでに証明された主張を根拠にして、新たな主張を次々に証明していくという、完全に演繹的な論理構成を取ったのです。その演繹的な論理部分については、後世の私たちが読んでも、ため息が出そうなほどの完成度を誇ります。
つまり、ソクラテス式に表現すれば、ユークリッドは、幾何や数論などにおける様々な主張を問答法によって、関係するより確かな命題、それらを組み合わせると根拠になるような命題に突き付めて分解していきました。そして、それを整理すると、幾何学、数学のすべての主張はほんのいくつかの、誰もが受け入れざるを得ないような命題、それのみを根拠としているということを発見したのです。そこで逆に、そのほんのいくつかの命題、つまり、公理や公準から議論を始めるように、証明を再構成することによって、誰にも反論の余地がないかのような、洗練された幾何学、数学を完成することに成功しました。ある分野において公理、同じ意味ですが原理を発見することができること、さらに公理や原理からすべての主張を演繹することで洗練された理論体系を構築することができること、これらの論理的な方法論の有効性を知らしめたことが、ユークリッドの原論の最大の功績と言えます。例えば、日本にも江戸時代には和算、算術と呼ばれる微分積分まで独自に発見していたという、進歩的な数学がありましたが、他の学問と同じく、様々な知識はありましたが、それらは個別に論じられ、ユークリッドの原論のように、根拠を明確にして論理的に隙のない体系を構築しょうとする姿勢や興味は、あまりなかったようです。
上記のように書くと、ユークリッドの原論が机上の議論や論理のみで出来上がったような印象を与えかねませんが、実際は、その内容からも計算、作図、測量、実験などの経験的な知識に裏付けられた研究だったはずです。このページで以降に述べる論理に関連する用語や考え方について、詳しくは後の論理の章で説明したいと思いますが、ユークリッドは、断片的に経験的に知られている様々な幾何や数論の知識から帰納的・演繹的な推論を繰り返して、公理や公準を見つけ出していったはずです。つまり、雑多な知識の中から、無関係な知識を捨象し、関係ある知識のみを見つけ出すために、公理を見つけては演繹的に推論して、推論された命題に矛盾が生じないか、実際の経験的な知識と整合するかを確かめ、矛盾するなら捨て、合致するならば採用するという思考の繰り返しを行ったと思います。その際には、思考実験だけではなく、多くの計算、作図、測量、実験も繰り返す必要が生じます。したがって、ユークリッドの原論を机上の議論のように感じるのであれば、そのような計算、作図、測量、実験などの経験が乏しいからと言えるかもしれません。
逆に、ユークリッドの原論を絶対的に正しい理論のように感じるのであれば、さらに根本的に、物事を抽象化し、体系化して理解することにまだ慣れていない、つまり、その利点と欠点あるいは限界を理解していないと言えるかもしれません。けれど、それを理解することは、ここまでこの文章を読まれてきた方には簡単なことだと思います。最も大切なことは、知識をあくまでも仮定として捉えること、つまり、ユークリッドもソクラテスの無知の知を土台にしてユークリッドの原論を著述しただろうことを理解することです。ユークリッドがソクラテスの無知の知の忠実な影響下にいたことは、元々、ギリシャ語の『公理』という言葉は「要請」、『定義』という言葉は「仮定」という意味であって、後世の人々が現在の『公理』=「誰もが認める自明なこと」、『定義』=「意義の説明」という意味に置き換えてしまったらしく、そのような権威主義に陥った後世の人々による言葉の意味の歴史的な変遷を遡ることで、はっきりと読み取れるだろうと思います[参考文献:たのしいすうがく2 不完全性定理 数学体系のあゆみ,p26]。つまり、ユークリッドは、彼の原論のいわゆる公理や定義、つまり、「要請」「仮定」に根拠がなく自明でないこともきちんと意識していたわけです。したがって、ユークリッドの原論は、ユークリッドが知りえた幾何学や数論の知識、突き詰めると計算、作図、測量、実験などで得た知識による仮定であり、とても優れた仮定であっても、そこには適用範囲もあれば、誤差もあり、それ以外の理論体系もあり得るということを否定していないのです。
このように、一般的に物事を抽象化し、体系化して考察する際には、その枠組みをあくまで仮定として捉えて、その確実性や適用範囲、別の体系の可能性を検証することを忘れないことが大切になります。この姿勢があって初めて、一つの洗練された仮定や論理の体系からその推論による利点を得られるのだと思います。そこで、仮定や論理を絶対視すれば現実に対して盲目に陥る危険が、常に生じるのだと思います。他方で、現実との齟齬が生じる危険があるからといって、疑問を持って仮定を立てたり、論理体系への理解を深めたり、適用できるか試したりすること自体を放棄してしまえば、様々な可能性、正確性、効率性があるはずなのに、ある所から先について考えることをやめてしまったり、曖昧に物事を考えてしまったり、二度手間、三度手間で、結局は時間がかかってしまったりするのだろうと思います。簡単に言うと、前者の弊害は過信して考えを絶対視すること、後者の弊害は間違いを恐れて考えることをやめてしまうこと、であると思います。さらに極端に言えば、すべての人が多かれ少なかれ陥ることですが、前者は自分で考えたことや教えられた一つのことを信じ込んでしまって修正できないこと、後者は知識を整理したり推論したりすることが難しいからといって、自分で考えるべきことの多くを放棄して、経験や直感に過度に頼ったり、定められたことを行うだけになってしまうこと、と言えるかもしれません。
両者は異なるようでいて同じことで、前者に陥りがちな人は後者にも陥りがちで、逆に、前者、つまり、理論や考察を複数の仮定として正確な理解と共に利用できる人は、後者、つまり、様々な理論や考察を仮定として創造したり援用すること、そして、物事を仮定として論理的に整理したり推論することも得意だろうと思います。なぜなら、両者は共に、考えること、つまり、問うという行為を上手くできているかいないか、しているかしていないかという点ではまったく同じだからです。つまり、時間や状況の制限はありますが、仮定はいくら立てても、そこからいくら推論してもよく、逆に、その仮定や推論が間違っていればいくら否定しても構わないわけです。そこでは、常に問うこと、観察と検証さえ怠らずに、何がどのくらい確実なのか、確実でないのかさえ分かっていれば、原則的には結果としての間違いは生じずに、観察、仮定、推論、検証の繰り返しの中で仮定と推論の精度を高めていけるのだろうと思います。さらに言えば、検証できないのならば、検証できないというところで止めて置けばよく、検証ができないから初めから考えないとか、逆に、まったく検証ができないことを延々と考えるとか、検証できないけれども正しそうだから実行してみるとか、検証していないのに正しいと思い込んで実行してしまうなどという姿勢は、好ましくはないのだと思います。
以上のことからも、私は合理主義の最も簡単な定義を、真実又は真理を追及して、謙虚に問い、誠実に確認することとして、問うて観察から仮定を立てること、立てた仮定やそこからの仮定的な推論を改めて問う、つまり、確認や検証をすること、その両面の重要性を表現したつもりです。このように考えると、そのどちらの意味でもギリシャの合理主義の出発点であるソクラテスの問い、無知の知は、現在でも学問の根本を支えているように思えて、ソクラテスの慧眼に感じ入ります。
次のページ:学問と論理10(西洋近代と現代の合理主義1) -なぜ・なにを・どう学ぶのか-
目次へ
公開日時:2016年8月27日
修正日時:2017年3月17日 章立てを追加。「民主主義とリベラル・アーツ」を修正。
修正日時:2018年3月02日 新しい内容を追加して、ページを分割。
最終修正日:2018年3月02日