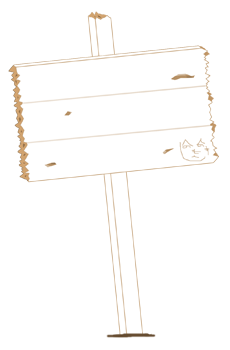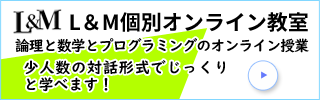数学の証明の記述法について
交換子群についてを書いていて思ったことは、数学の証明の記述の難しさだ。
何が難しいかと言えば、証明の論理をどこまで詳しく記述するべきかということだ。
詳しく書けば煩雑になり、読むのに時間もかかる。かといって、省略しすぎれば分からなくなるし、その行間を埋めるために余計に時間がかかる場合もある。誰でもポイントを押さえて簡略な資料を読みたいのだから、そして、その分野に習熟すればするほど「当たり前」のことが増えて、結果的に初学者に負担の大きな本ができあがることになる。
歴史を見ても、リーマンの有名な素数についての論文は非常にパブリックな論文であったのにも関わらず、その後、百年以上(今でも?)、その論文を検証するために多くの数学者の手間と時間がかかってしまっている。その辺の機微や歴史的状況には詳しくないが、そういうことが起こり得てしまうのが数学という学問の危険な側面だ。
数学は、ほぼ人間の頭のみで事実検証をする科学なので、他の数学者が検証しえない上記のような状態は、数学的成果の科学的な側面を危うくするので、できるだけ避けなければならないのだが、実際には優れた数学的成果であればあるほど、この検証困難のリスクが大きくなる事態が、しばしば起こる。ガロアや現在の望月氏など、枚挙に暇はなかろう。
数学論文の書き方について、標準的な理論がありそうだが、というかあるべきだと思うのだが、例えば、公理主義的な立場で、すべての命題を書き出していけばよい、という主張が聞こえてきそうだが、事はそんなに単純ではない気がする。つまり、ある数学的な事実を述べようとするときに、その述べ方、表現の仕方、捉え方は幾通りもあるはずで、さらに、どこまでを命題として採用し認めるべきかということにこそ、最も大きな問題が横たわっている気がするのである。
そもそも、関係論理で述べたように、数学の命題が言語に依存している限り、その言葉、命題は相対的な関係によってしか規定されない。したがって、公理を立てたとしても、その公理といえども相対的な曖昧さを生じるのであって、さらに言えば、公理から演繹される命題間の真偽については、公理から自明と言えるのは、ある意味、主観であり、本来は、いくらでも、新たな問いを行えば、命題の細分化が発生し、既存の公理の枠組みを超えていってしまうはずなのである。
では、数学的な記述のあるべき姿はどんなものかと言うと、
1.数学的な事実は、相対的で多様であり複数の捉え方ができる。
2.論理、つまり命題はいくらでも細分化することができ、尽きることがない。
3.検証する人間(読者)の理解水準を明確にする。
ことが必要なのではないかと思う。
そう考えると、数学の証明を記述する際には、次のような作業フローがあればよいのではないだろうか。
1.できる限り、様々な考え方、証明法を列挙する。
2.できる限り、命題を細分化する。
3.読者の理解水準を一つあるいは複数、想定する。
4.読者の理解水準で最も見通しの良いシンプルな証明法と論理展開を提示する。
5.上記で理解できない読者のために、詳細な命題を加えた論理展開の詳解を提示する。
6.読者に深い理解を促すために、その他の証明法を別解として提示する。
どのような形であっても正解、詳解、別解があれば、読者としても自分のレベルにあって、その数学的事実を検証できるはずだと思う。
例えば、別の論文、別の本、ウェブ資料、どんな形であってもそれは良いと思う。
新しい数学的真理を発見したり、時に新たな数学的な枠組みを発見することも数学の発展だが、既存の数学を容易に理解できるような枠組みとして再発見・再定義することも、数学の基礎を形作る大切な進歩であると、数学史を振り返ると感じる。
数学の科学的な側面、検証可能性と知的恩恵をもたらすのは、どちらの貢献の方が大きいのか、あながち前者であるとも断言できない気がしてくる。